こんにちは。
経年風アクセサリー素材のお店*よつば商店
店長のシバガキです。
今日のブログでは
2019年6月に訪れた
チェコ国立プラハ美術工芸博物館について
書いてみようと思います。
2019年6月の買い付け旅行中に半日ほど
時間が取れたので現地の友人に
どこを観光しようか相談したら
「チェコのガラスなどの
工芸品に興味があるなら
一度行ってみるといいよ」と
チェコ国立プラハ美術工芸博物館を
おススメされたので行ってきました。
チェコ国立プラハ美術工芸博物館
(Uměleckoprůmyslové museum)
略してUMPRUM
URL: https://www.upm.cz/
場所はこちら
https://www.prague.eu/ja/object/places/627/umeleckoprumyslove-museum#showMap
(プラハ市公式観光ポータルより)
博物館のお向かいには
チェコフィルハーモニー管弦楽団の
本拠地、ルドルフィヌムがあります。
↑こちらはルドルフィヌム(Rudolfinum)
肝心の工芸美術博物館の外観の
写真をとっておらず………
ルドルフィヌムも工芸美術博物館も
どちらもネオルネサンス様式の建物なので
雰囲気が似ていました。
たぶん。(記憶が曖昧)
私は音楽のことは全然知らないのですが
毎年春に行われるプラハ音楽祭は
こちらがメインの会場だそう。
一度本場の演奏を聞いてみたいです😃
さて、早速博物館の中へ。
入り口の扉の大きさに驚きつつ
中へ入ると…
建物自体が立派な展示品という感じでした。
通路も階段もすごい…
朝イチで行ったので人もいなくて静か…
館内は数年前に
改装されたばかりらしく
100年くらい前の装飾品も
色鮮やかで美しかったです。
確か5階建くらいの建物だったと
思うのですが
フロアごとに様々な展示がありました。
まずは常設のガラスの展示を見学。
撮影OKだったので少しご紹介します。
PLEIAD OF GLASS 1946-2019
1946年から2019年までの
ガラス作品が展示されていました。
中には
「え、これガラスなの?」
って思う質感の作品もあったりして
見応えがありました。
チェコのガラス産業の歴史、
アートとしてのガラスについてなど
英語での説明もありました。
次に別フロアで開催されていた
テキスタイルの展示も見学。
北斎の波モチーフの生地。
とてもおしゃれ!
外国で日本由来の物を見ると
なんだかテンションがあがります↑
こちらも日本の
傘をモチーフにした生地。
おしゃれだなぁ…
様々なフラワーモチーフ。
昔は60年代のファッションに
憧れていました…
素朴で愛らしい模様。
色の合わせ方などは
アクセサリー作りの参考にも
なりそうでした。
動画でわかりやすく
ファッションの歴史の移り変わりを
解説する展示やもあり
知識がなくても見て楽しめました。
ファッションやテキスタイルの
知識があったらもっともっと
楽しめただろうなー。
長くなりそうなので
今日はいったんここまで!
次回は別フロアの
一風変わった展示や
館内を撮った動画をお見せできたらと
思っています😃
読んでくださりありがとうございました🍀
経年風アクセサリー素材のオンラインショップ
よつば商店
https://yotsuba-and-co.jp/
商品入荷のお知らせやお得なクーポンを
お届けしているメールマガジン登録はこちらから↓
https://yotsuba-and-co.shop-pro.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01114554
Twitter
@yotsubashouten
Instagram
@yotsuba_and_co








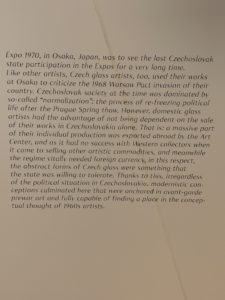




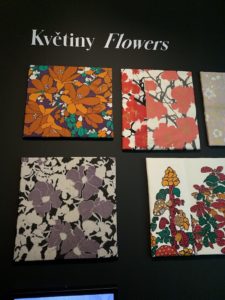
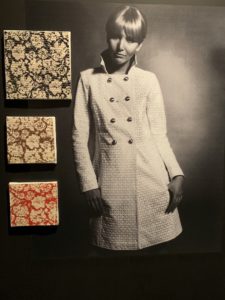






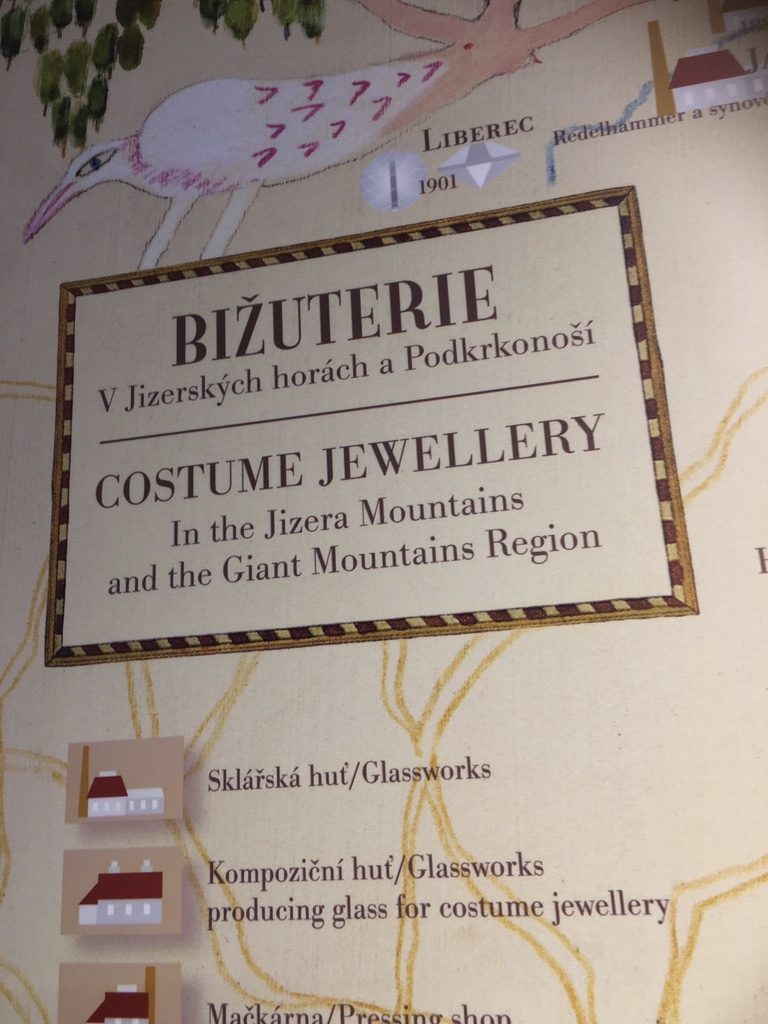
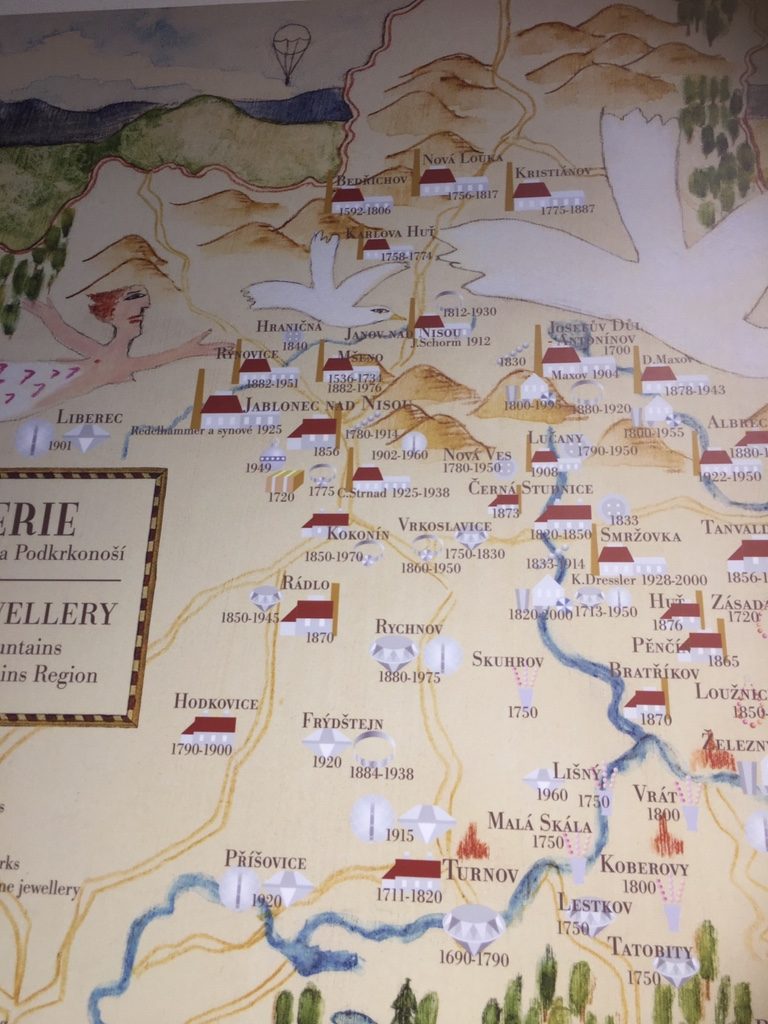








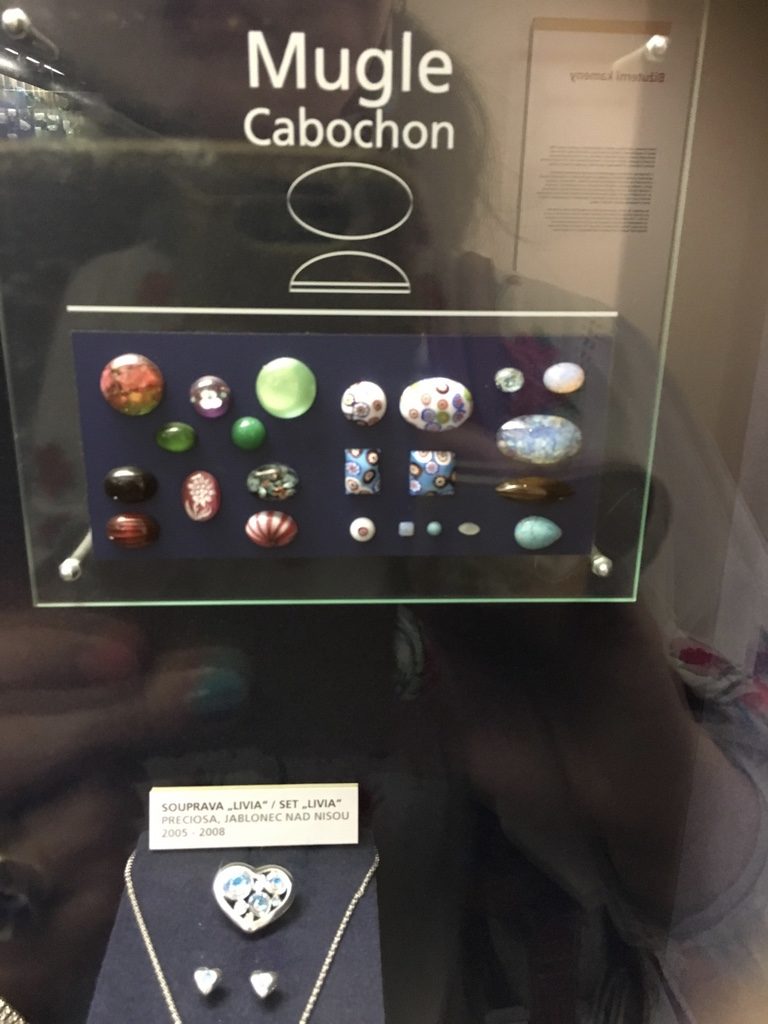
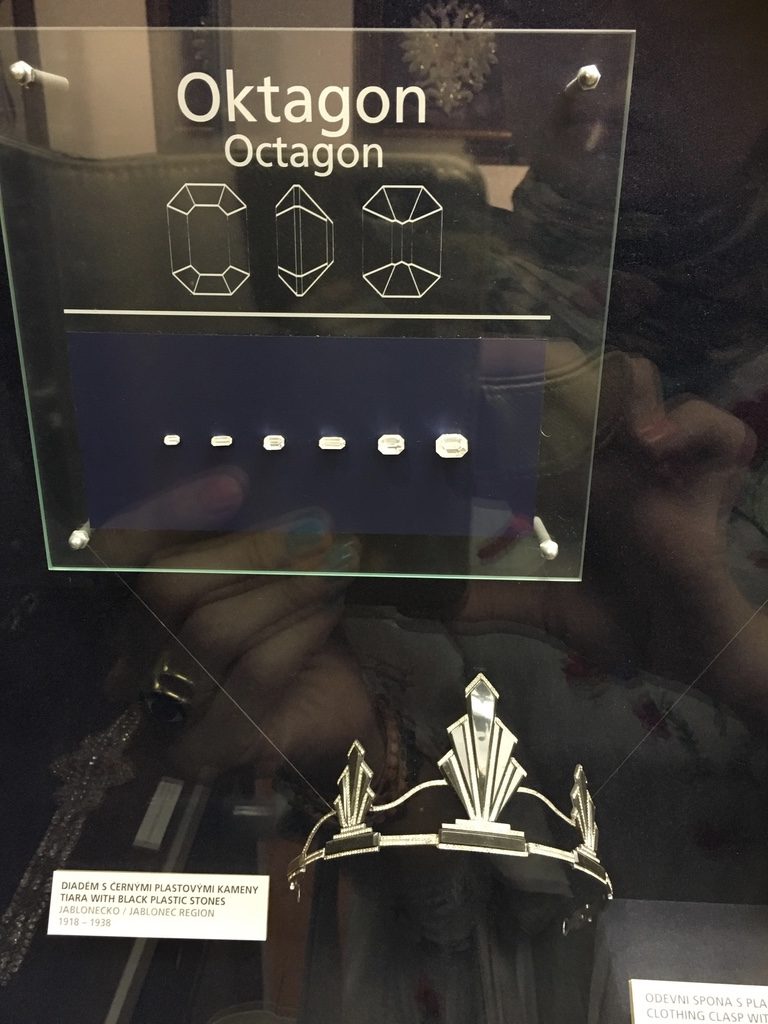
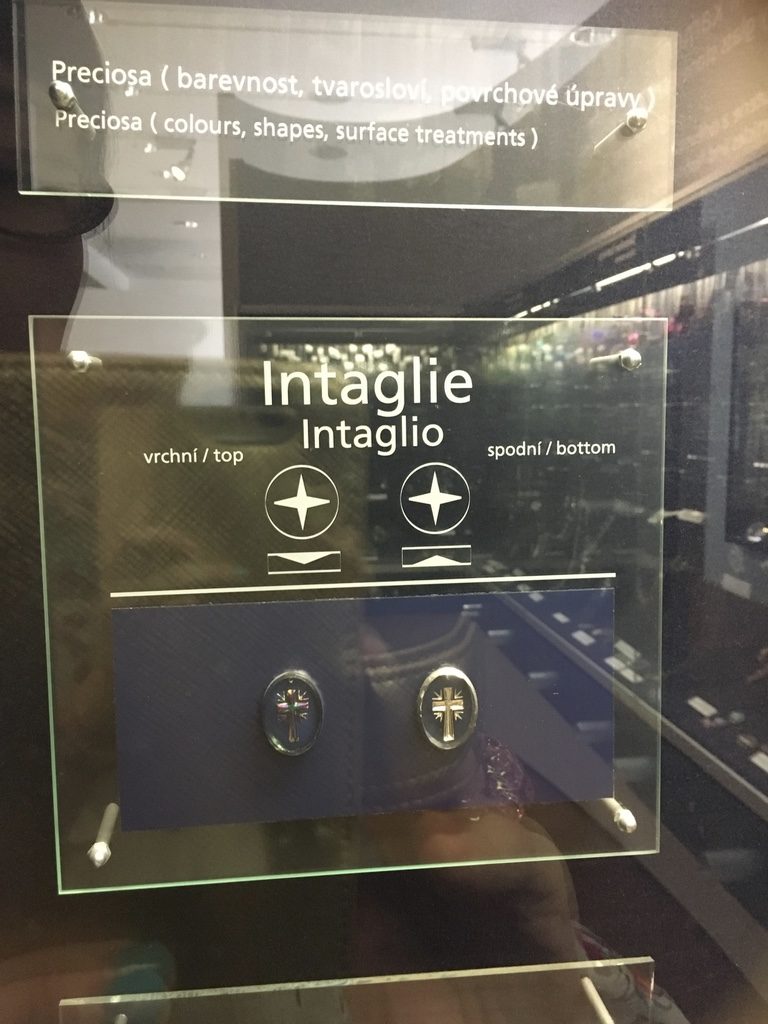



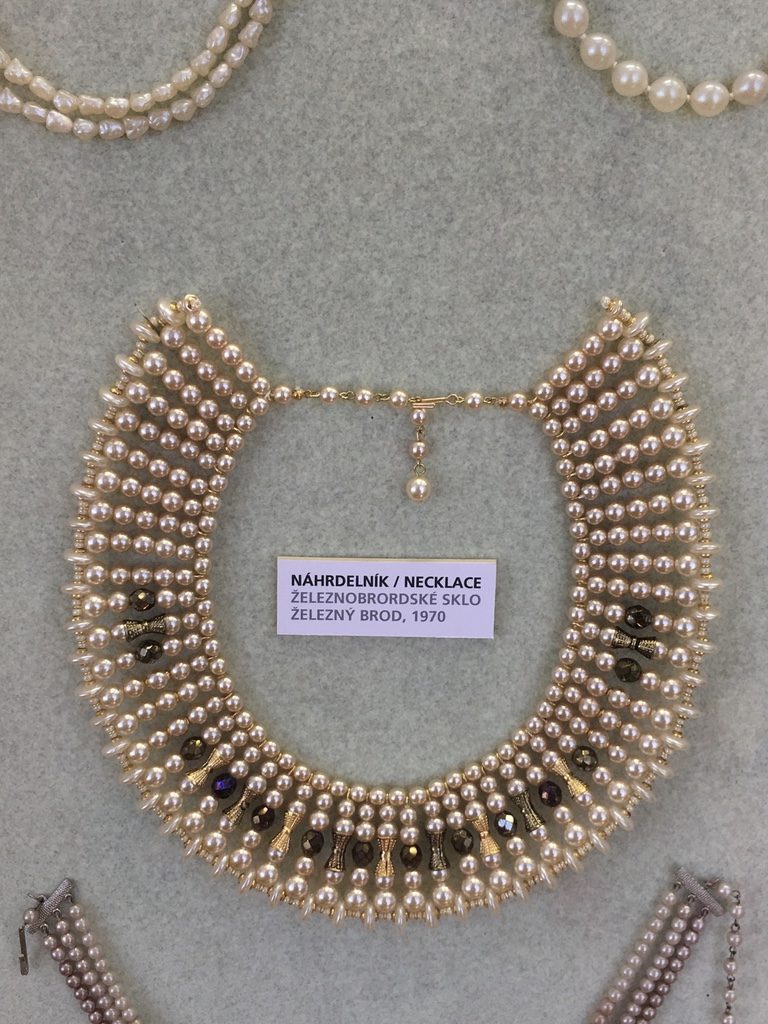

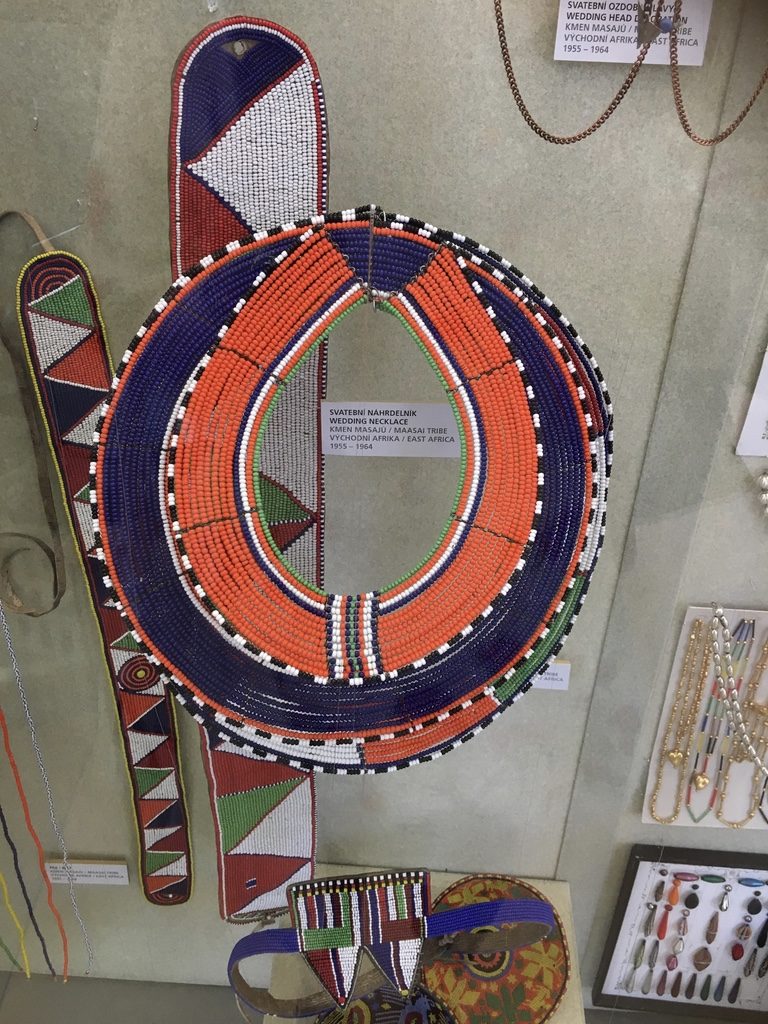


最近のコメント